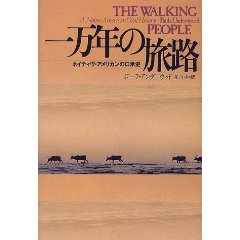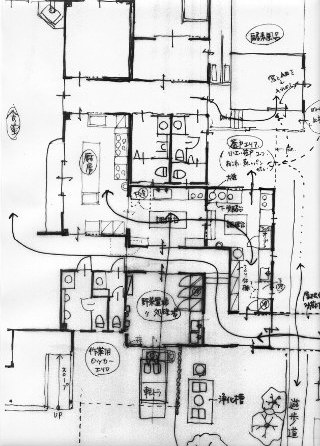メンバーののりちゃんが、「今、とてもいい本を読んでいるのよ」と嬉しそうに教えてくれた話を、ぜひ皆さんにも紹介したいと思い、ブログに載せることにしました。本のタイトルは、「一万年の旅路 ~ The Walking People」、イロコイ族に伝わる「口承史」です。歩く民、ネイティブアメリカンの物語は、木の花の精神性にも深く通ずるところがあります。ではご一緒に、「読書の秋」を楽しみましょう!
—
「彼女は母」という名前の女の人がいるの。お母さんという意味ね。なぜその名前がついたかというと、その人にはパートナーがいるんだけれど、ずっと子供ができなかった。でも子供が好きで、木の花のあっちゃんのように、子供は産まないけれど、子供たちのお母さんという意味で、それを象徴して、「彼女は母」という名前をもらっている。自分に子供がないことで、さらに子供たちに気を配るようになった。本当に分け隔てなく子供を育てて、子供たちに関わっているの。
それである時、彼女のパートナーも自分たちはひとりの子供も授からないけれど、みんなの子供の父親になろうとふっと思ってね。自分にできることは何だろうと思ったら、自分たちがこれから行く先に、どっちに行ったらいいだろうか、どこに食べ物があるのか、要は探索隊としてあちこち調べてまわるチームがいてね。彼は、自分は結構歳もとっているけれど、若者たちに知恵は貸せるだろうって、そのメンバーに入るの。
その若者たちは、「そうか、このおじさんが来るのか、ちょっと足手まといだな」と思うところもあった。でもそうではなくて、やっぱりこの人の知恵を活かすためには、多少全体の足取りが遅くなっても、この人とともに行こうということになったの。
ある時、探索隊で行った人たちが危ないところへ行って、結局帰ってこなかった。その時、その女の人は子供が宿っていることに気がつくの。長いこと子供を授からなかったのが、今なぜ宿ることになったかというと、長い間パートナーと離れることによって、愛情が育まれて、ふたりが良い関係になったからなんだよね。近くにいるからパートナーじゃなくて、離れているからこそ、想いがいろいろあったり、離れることによって、ふたりの絆が強まって、そこで子供を授かるということになる。でも、そのパートナーはもう帰ってこない人になってしまった。
「彼女は母」は、「悲しみよりももっと大きな目的があります」と言って、一族に心配りをする。その女の人の子は無事生まれるんだよね。ところが、生まれたら、その子は身体障害者だった。表現としては、「ねじれた足」っていうふうに書いてある。だから、歩けない。ネイティブアメリカンのならわしでは、体の不自由な子は連れていけない。歩く民だから、とにかく歩かなきゃ進めない。だから、全体のことを考えて、足手まといになるその子は置いていく。要は、森の中に捨てるということだよね。
~愛情と思いやりを持って、生まれたばかりの歩けない人に付き添い、われらが大地とひとつになる。あの「大いなる眠り」へと導く~(本文より)
でも、お母さんとしては、捨てるのは辛い。だから、民の長老が、辛いのを承知で捨てにいくの。でも、その長老も彼女にそれを言いだしにくい。なぜなら、父親になる人がもう帰ってこないという痛みを、彼女は既に持っているから。その上に、せっかく生まれた子供を捨てにいくという二重の苦しみを与えたくないと、その長老がすごく辛い想いをしているの。それを想い彼女が、「長老の悲しみのほうが、私が想っている悲しみよりもきっと深いだろう」と。だから、長老がその役割をするよりも、自分がその役割をしますと伝えた。
でも、私の足に人を運ぶことを学ばせて下さい、この子にも私は可能性を求めたいって。今は足が歩けない状態だけど、だから、その分私がこの子の足になって面倒を見ますって。でも最終的に、この子はやっぱりみんなの足手まといになって連れていけないという判断をした時には、私が責任を持って森に連れていきますということを言ったの。
日々の行いが素晴らしい彼女を一族が認めていて、そして、その彼女が「生命の贈り物」を森で眠らせて帰ってこれないことがあったら、一族全体が彼女の得難い心づかいを失ってしまう。彼女がさらに決心を伝える。
それで話が成立して、一緒に行動するんだよね。だんだんその男の子は成長していく。足で歩けないから、手も使って這った状態で、いろんなところへ移動するんだけれど、結局遅いから、お母さんが肩車で移動する。そのうち、その子も知恵がついてきて、お母さんが肩車しやすい位置に乗って、そうやってその子なりに知恵を使うの。
~四本足の踊りをして、生きる糧を探す。いとも見事な掛け合いの踊り。志の確かな2人の人間の間に、どれほど大きな協力が生まれ、そういう協力が不可能を可能にするかを学び、理解する~(本文より)
ある時、いくつか年齢は書いてない。「幾度の季節を巡り」という書き方をするから。その子が大きくなっていくにつれて、体重も重くなるから、そのお母さんの腰がだんだん曲がってきた。その子を降ろしても、腰が伸びなくなっている。母さんの曲がった背中と、僕のために食べ物を探している人たちに申し訳ないと言って、その男の子がものすごく悲しむんだよね。
その男の子は、もしお母さんが死んだら、母さんが横たわった所へ僕もとどまり、できるだけ自分も生きのびて、最後は「大いなる眠り」でまた会おうと。でもお母さんは、「歩けない者でも、鷲のように飛ぶことはできるかもしれない。私の言う意味がわかったら、その時こそおまえは、自分にとっても一族にとっても、大きな荷物ではなくなるんだよ」ってヒントを与えた。
そうしたらその子は、自分なりに考え、鷲というのがヒントになって、ひっそりと群れから離れてずいぶん長く帰ってこなかった。みんなが心配するんだけれど、その子は遠くで鷲の巣を見つけるの。雛がいて、お母さんがえさを運んでっていう、鷲の子育てをずっと見ていた。鷲が持ってくるえさとか、季節が変わるたびに食べ物も変わることとか、そこで食べ物について勉強していた。
その子がみんなのもとへ戻った時に、「わかった、僕がみんなの食べ物の毒味をする」って言うの。その子には、そういうセンサーがあって、どの食べ物がみんなにとって良いか見極めることができた。自分でそれに目覚め、体が不自由でも、その子はみんなに当てにされるくらいの知恵を授かったことに対して、3本の鷲の羽を贈って敬意を表わす。
体が不自由でも、「自分が活かされる」ということに目覚めれば、本当の意味で役に立つ。本来は、体の不自由な子は一緒に行かないんだというネイティブアメリカンの掟があったんだけれど、みんなの愛で、一族の掟も変えられた。みんなが他人を想う心が常に根底にあり、母の痛みが一族の痛み、一族の痛みが母の痛みとなる。また、歩けない子供の痛みが母の痛みとなり、母の痛みからその子は自分を活かし、他人のためになることを学ぶ。
やはり自分で目覚めないと、同じ不自由をもらっても、「こんな体になんでなるんだ」ってそこで不満が出ると、いただいたことの意味がわからない。活かすためにあるんだと気づき、自分がみんなのために何かをしたいと思えば、自分が活かされ、みんなが喜ぶ。
自分のやりたい役割が与えられなくても、でも何だってみんなを代表して今ある役割をしているわけだから、そこに感謝の心があれば、何も沈むことはないんだよね。
パートナーがいて子供を授からなくても、みんなのお母さんにもなれる。誰から言われるわけでもなく。自分のやれることで、みんなの父親になり、若者たちに知恵を与え、そしていのちも厭わない。
私がこの本を読んで思うのは、ネイティブアメリカンの人たちは、いつも命がけと隣り合わせ。ただ歩くんじゃなくて、そこには危険な崖もあって、子供を連れていくにはどうするかとか、すごく知恵を使う。
それをみんなで話合うの。そして、事があって何か痛い思いをすると、「学ぼうではないか」というのが合言葉なんだよね。悲しみに暮れないで、「学ぼうではないか」ということを、いつも誰かが言いだすの。その時その時、きっかけになる人はいて、いろいろ提言する人や、痛い目をする人やら、いろんな役割の人がいるんだけれど、でも全体の空気としてはその出来事をもらって、ちゃんとステップになるのね。
そして、彼らはすごい距離を歩く。それも命がけの。今、木の花に命がけということはないよね。でも、そのネイティブアメリカンの人たちは、自分たちのひとつの発言やひとつの行動が、みんなの命にかかってくるわけ。だから、最近いさどんの言う「真剣」というのは、彼らからしたら、まさに毎日が真剣で、食べ物ひとつ食べるにも命がけなの。毒いちごを食べたら、食べた人みんな死んでしまうわけだから。そういう意味では本当にみんな真剣で、だからこそ、大人も子供もみんなで話し合うんだよね。女だから黙っているとか、そういうことはない。まさに、命がけの人生をみんなで生きていて、子供ですらそうなんだよね。
悲しいのは、歩けない赤ちゃんをみんなで背負って進んでいくんだけれど、それでも、歩いていくととても危険な場所があるの。それこそ、ひとつ間違ったら崖から落ちるというようなところも歩いていく。
その時に、子供と老人を置いていくという決断もしないといけない。でもその老人たちは、この子供たちにここで知恵を残して、育てていくという役割をする。前に進む人たちもそれを託して、自分たちはもっと一族が安心できる地を求めていく。
形を見ると二分されるんだけれど、でも心はひとつ。それぞれ場所は違っても、形は違っても、ひとつの心でその形が成り立っている。これから、木の花からも綾部やいろんなところへメンバーが移動したとしても、一緒のことだよね。