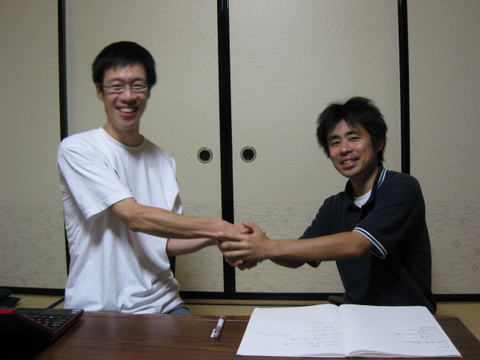自然農法センターの1泊2日の宿泊の所外研修を木の花ファミリーで行いました。見学・コンサート・大人会議への参加・作業体験・振り返りと盛りだくさんの内容でした。 始めは、硬い感じだった研修生も最後には、ほぐれて表情も明るく、そして、いろいろな話をしてくました。
ちなみに、8年前、僕は、自然農法センターの研修生でした。そこで、わたわたに出会い、育種を学び、農業の奥深さを知りました。その時から、目標はエコビレッジづくりでした。8年たった今、その時に描いた以上の現実が木の花ファミリーで展開しています。
とても楽しい時間でした。研修生の皆も色々と話していくうちに、自分が何をしたいのかを内側に問いかけ、自分自身のこれからのことを深めている様子でした。

作業体験では、トマトのハウスで芽かきと誘引をしました。水稲を勉強しているみんなは、木の花のたくさんある水田の見学にいきました。

とまとの芽かき中

作業の合間の休憩タイム。メンバーと研修生の交流の時間。いろいろな質問や話題が飛び交いました。

トマトの作業体験を終えて、一枚パチリ。みんな暑い中お疲れ様でした。

木の花からは、いさどん、こうちゃん、たっちゃん、まこっちゃんが参加して、研修生達と、今回の研修の振り返りの時間を持ちました。みんなから様々な面白い感想がでました。
・自分の持っていた枠が壊れました ・単なる自己実現だけでなく、社会貢献ができるように、大きな視点で農業をやっていきたい ・物理的なことの奥にある心を大切にしているところに感銘を覚えた・・・などなど。それぞれの視点から、様々な意見が聞けて僕等もたのしかったです。
ちょうど、いさどんが今年から公益財団法人自然農法国際研究開発センターの外部理事をつとめることになり、より木の花としても、自然農法センターと連携をしていく流れができているのだと思います。たんなる技術ではない、自然農法の魅力や深みを広めて生きたいし、自然農法の奥にある世界観、宇宙観といったもの、宇宙の法則を生活の中に生かしていくひとつの事例として活用して貰いたいし、共に活動していきたいなと思ってます。
以下は、わたわたがブログであげてくれた木の花での研修の記事です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
自然農法センターの研修生の所外研修の一環として、木の花ファミリーを視察に来ています。木の花ファミリーで実践されている自然農法の稲作や畑作、発酵飼料・地域資源を活用した採卵養鶏、農産物の宅配販売、加工品製造などをコミュニティとして複合的に運営をしている現場を視察しようという研修です。自然農法センターの考えている自然農応は、単なる栽培技術ではなく、自然を規範とし順応する農業のあり方であり、その農業を成り立たせ得る社会づくりをも含むものです。で、その自然をモデルとする営農方法・暮らし方のひな形の1つとして、農業を基盤としたエコビレッジがモデルになるだろうと思われるわけです。というわけで、エコビレッジの実際を経験しようとやって来ました。


農場や施設を見学させてもらい、その後、農業や暮らし、自然をモデルにするという精神性についてプレゼンを聞きました。理想論だけで考えると、共同の農場運営や生活は経済性や環境負荷を少なくという観点では素晴らしいけれど、それを実際に行おうとすると、例えば血縁のない農家数軒が共同生活体を作れるかというとそれは難しいと誰もが思うでしょう。では、例えば経営者と労働者という会社のような人間関係ではどうかというと、家事労働にまで労賃を払っていたら成立できなくなってしまう。企業体ではなく、構成員がみなフラットな関係で事業から生活まで全て共同するということ、すなわち血縁を超えた人々が同じ理念のもとに、家族として暮らすことで成立しているのがエコビレッジというあり方、その1つが木の花ファミリーです。
自然をモデルにした農業にはいろいろな形態があっていいし、農業と暮らし方を一致させる方法としてのエコビレッジにもいろいろな形態があっていいのだけれど、いずれにしても、その当事者は人間であり、人と人との関わりで運営されるということ。つまり調和的に生きる、暮らすという心が一致していなければ成り立たない。何をどうつくるか、どんな事業をするかも大事だけれど、それをどんな心のもとに行うか、何を大事にして人が集まるのかが、継続できるかどうかの鍵を握っていると言えるのです。一見、農業に無関係なように思われる心の在りようが、実はそこにどんな農業の形を呼び込んでくるかを決めている。それは宇宙の絡繰りだと思います。
「畑を耕す前に心を耕せ」という木の花ファミリーで良く語られる言葉の意味するところを聞き、自然農法の理解を深めてる研修の一環としました。自然農法で農業をしていく、自然農法で暮らすということは、まず自らの心が自然を規範とした在りようなこと。自然は利他の仕組みで成り立っています。すなわち生態系全体が調和的になることに貢献する種族が進化を許されていく。自分や自分の身近な存在と同じように他人や社会や地球のことを考える。そのなかに農業として必要なことを見出していくなら、それが農法・技術となるのでしょう。自然農法は単なるテクニックや特定のやり方のことではなく、その都度現れる自然に合わせていくということ、その地の農業としての役割を果たしていくこと、そこにどう向かい合うかという姿勢・心のことだと思ったのでありました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・