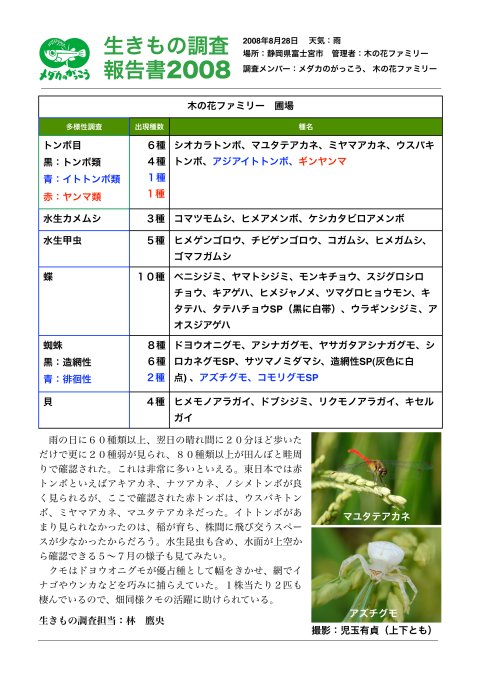今年は、光合成細菌の安定培養ができるようになったので、育苗時、葉面散布などに積極的に混ぜています。
その成果、こころなしか苗もがっちりした苗が育っています。畑に出しても今年のキャベツやブロッコリーはなぜかでかい!!外葉がガッシリしており、かといって色が濃いわけでなく淡い色をしている
施肥を増やしたわけでもないのに、なぜだろうと思いながら見ていました。虫害も去年に比べると少ないように思う。やはり光合成細菌の影響がでていると考える方が妥当なようだ。
キャベツ。品種は若峰
キャベツ、ブロッコリー畑
この写真ではいいところをとっていますが、もちろん、虫害のでているところもあります。比較的、苗の出来の良いところの虫害は少ないようだ。
ちなみに、自然農法センターの石綿さんに聞いたころによると、(うる覚えかもしれないのであしからず・・・・・。)
苗の時に光合成細菌を使うと、苗土の中の低栄養のものを好む微生物(ミネラルなどを好む微生物)が活性化される。光合成細菌がそれらの微生物のえさになる。
ちなみに、乳酸菌や酵母主体の活性液を使うと、乳酸菌や酵母は高栄養なので、高栄養なものを好む微生物が活性化するそうです
光合成細菌をえさにして地味な微生物たちが増えると、苗土の養分を使いながら増える。そうすると作物と微生物がせめぎあいながら養分を奪い合う。苗土には、養分はあるんだけれど、微生物さんたちが利用しているからなかなか吸えない。なので、より毛細根をのばすことでなんとか養分を吸っていこうとする。そうなると、がっしりとした苗になるそうです。
よく、無肥料で栽培をする人がいますが、そういうところで成功している作物は、ない中でなんとか根を伸ばして養分を吸っていこうとするので地上部ががっしりして虫につかれにくい作物になるようです。
光合成細菌を使うとそれに似たような状況になる。あと、光合成細菌は多糖類の膜をつくっていて、グルカン?っていう成分があって、それが植物の根に触れると、攻撃をうけているような錯覚をうけて、それに対抗するためにグルカナーゼという成分をつくるらしい。そのような免疫機能を上げるような回路が発動すると、同時にいろいろな防御機能が発動される。たとえば、だぶついている養分を減らせー!!とか、クチクラ層をあつくしろー!!とか、病原菌から身を守れーみたいな指令が発動するので、結果的に健康な苗になるそうです。そんな感じで光合成細菌を使うと、風が吹けば桶屋がもうかる的な効果によって、健康な苗になる。
そんな苗を畑に定植すると、環境適応能力も高く、いい感じの成長をするのではないかと感じます
石綿さんがもってきてくれた、きゃべつの苗は、青虫が食えない。卵があってふかしても、クチクラ層が発達しているので食いにくいので餓死してしまうような状態がつくられるそうです。ただ、コオロギやバッタには食べられるようですが(笑)
ちなみに、うちの苗でもこれはと思うものは、虫もつかないし、強いて上げれば、やはりバッタやコオロギが食っているようだ。
光合成細菌、なかなか面白い!!引き続き試していこう!!