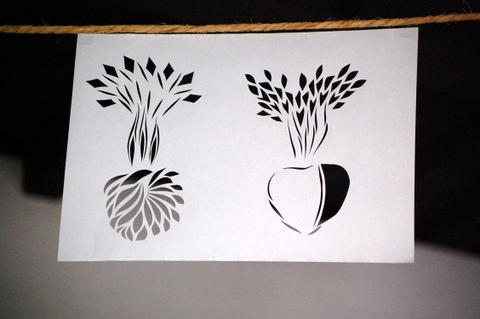ファミリーの中学一年生、須佐乃王が書いた夏休みの作文が、「第38回世界連邦推進全国小中学生ポスター・作文コンクール」の特賞に輝きました。すでに学校から知らせは届いていましたが、今日、地元の地域紙である「岳南朝日新聞」に大きな記事と作文の全文が掲載され、みんなで回し読みして大喜びしました。
私(いさお)は、須佐の国語の家庭教師をしています。いくつか挙げられたコンクールのうちのひとつを選んで作文を応募する、という課題が夏休みの宿題に出されたということで、ふたりで相談した結果、このコンクールを選んだのでした。
このコンクールは「次代を担う小中学生に平和の尊さを認識させるとともに」「人類の一員として意識をよびさまし」「『人間みな家族』『世界はひとつ』の精神を養い」「世界連邦について理解を深め」、「平和教育に資すること」を目的としているとのことでした。ふつうに考えるとなかなか抽象的で、生活に密着した文章を書くのは難しいテーマかもしれません。
でも、ここは「地球がひとつの家族になること」を目指し、日々の暮らしの中で実践している木の花ファミリーです。「僕らの生活なら、そのまま書けばOKだよね」ということになり、須佐は有機農業や環境への取り組み、そして心身のケアなどについて綴りました。
作文の中で、須佐は「世界にはふたつの平和がある」と書きました。ひとつは「戦争はないけれど、自分さえよければいい、それが平和だと思っている人が多い」世の中。そしてもうひとつは、「争いや戦争がなくなり、世界人類がみな家族になること」です。
「世界人類がみな家族になること」。理想として語られることは数多くあっても、実現が難しいそのテーマを現実のものとするには、どうしたら良いのか。私たちが社会に向けて提示し続けているこの生活の意義を、須佐は作文の締めくくりで見事に表現してくれました。
「ぼく達にできていることは、他の国の人々もこの暮らしが、できるんじゃないかなと思います。一人一人が自分のことばかり考えるのではなく、みんなのこと、世界のことを考える気持ちが持てるようになればいいと思います」
須佐は2月に東京で行われる表彰式に出席します。「地球家族」を目指す木の花ファミリーに生まれ、みんなの愛に囲まれて育った須佐。彼の存在は、その場の人々にどんなメッセージを伝えてくれるでしょうか。
 岳南朝日新聞 2010年1月20日
岳南朝日新聞 2010年1月20日
(以下、作文の全文です)
ぼくは、静岡県の富士宮市にある木の花ファミリーというところに住んでいます。
木の花には、57人の人が暮らしています。年齢層は、0歳の赤ちゃんから70歳のおばあちゃんまでがいます。大人は43人、子供は14人です。
木の花では、有機農業で自給自足をしています。大人の人にはいろいろな役割があります。農作業や事務仕事、食事作り、家事、家庭教師などです。木の花では、野菜を110種類、お米を10種類作ってます。その他に、にわとりを860羽飼っており、卵をにわとりさんからいただいています。ヤギやハチも飼っており、おいしいミルクとハチミツがしぼれます。しょうゆやみそも作っており、きゅうりや白菜、大根、かぶなどを使ってつけ物なども作っています。
自給自足の良い所は、環境に良いこと、旬のおいしい野菜が食べられることです。ぼくは学校の給食よりも木の花での食事のほうがずっとおいしいと思いますし、57人の家族の人と楽しみながら食べれることが気にいっています。
木の花では、野菜やお米を作るのに、農薬や化学肥料を一切使いません。農薬などを使わない理由は、まず環境や生き物、体に害をおよぼさないようにするためです。農薬を使わないと、生態系が豊かになり、虫を殺さなくても、作物が健康に育ちます。
木の花では、環境を汚さないために洗剤やシャンプーを使いません。他にも紙とゴミを分別したり、トラックをテンプラ油で走らせたりしています。
有機農業や自給自足が環境にいい理由は、いろいろあります。たとえば、有機農業では農薬などを使わないため環境をよごしません。また、自給自足では、近くで作物を育てるため、遠くの地域や外国からトラックや飛行機で運んでくるのと比べて、ほとんど石油を使わないのです。
多人数で暮らすとお金があまりいらないという利点があります。ガスや水、電気代が節約できます。また、自給自足をしている木の花では、食費がほとんどかかりません。
木の花では、一日の自分達の行動の反省などを毎日家族と話し合います。この話し合いをすることにより、子供や大人一人一人の心を育てて助け合いができる人にしていきます。良かったことや悪かったことについて他の人からアドバイスをもらったりもしています。ミーティングを続けていけばみんなの心がきれいになり、どんどんそれが広がれば世界が平和になっていくんだろうなと思いました。
木の花には、日本の人や外国の人が農作業をしたいと来たり、心や体のケアのためにたいざいしたりします。ケアでたいざいしたほとんどの人が、健康になって卒業していきます。また、木の花のメンバーに入りたい、という人もいます。ぼくは、木の花ってすごい有名だなと思いました。
ぼくは、平和に2つの意味があると感じています。まず、1つめは、戦争がないけれども自分さえよければいい、それが平和だと思っている人が多いことです。
2つ目は、争いや戦争がなくなり世界人類がみな家族になることです。
ぼくが、この世界連邦推進作文を書いて思ったことは、まず、みんなが心をきれいにしなければならないということです。まだまだ世界人類をみんな家族にするのは難しいと思います。でも、木の花では、みんなが家族になるという難しいことが50人でもできています。ぼく達にできていることは、他の国の人々もこの暮らしが、できるんじゃないかなと思います。一人一人が自分のことばかり考えるのではなく、みんなのこと、世界のことを考える気持ちが持てるようになればいいと思います。
この作文をつうじて、木の花ファミリーの生き方を世界中に広げていきたいと思います。